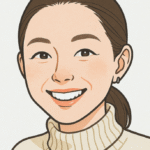精油を保管する時のチェックポイント

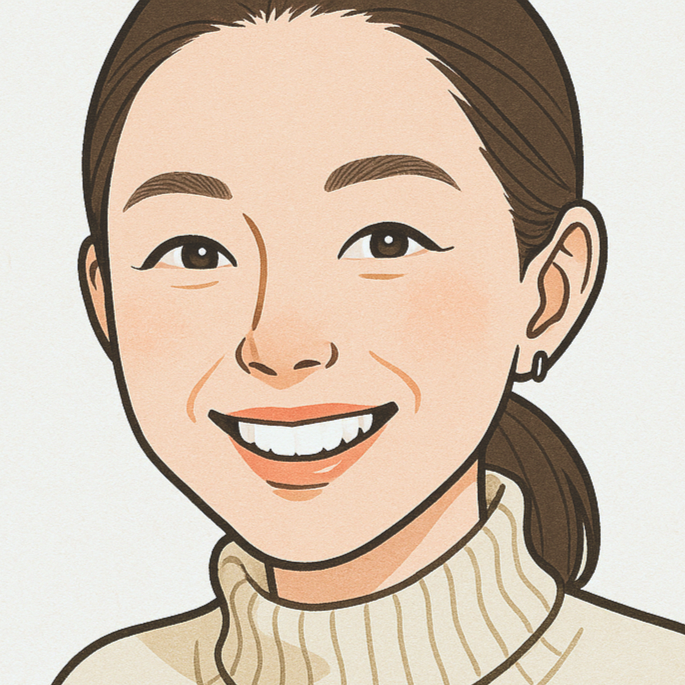
買ってきた精油、引き出しの片隅に転がっていませんか?
精油は防腐剤も入ってない、天然物。
もちろん保管方法を間違えてしまうと、劣化が進み、皮膚トラブルなど悪影響が及ぼす可能性もあります。
正しい保管方法を、チェックしていきましょう。
品質が変化する要因は、『酸化』『加水分解』『重合』
酸化は、空気中の酸素に反応して起こる成分変化。
酸化した精油は皮膚刺激が強くなり、アレルギー反応が出る可能性もあります。
また酸化は、光や高温で酸化が促進されます。
精油の成分の一つ、エステル類に水分が反応し、加水分解が起こると、カルボン酸とアルコール類に分解されてしまい、成分が変化します。
エステル類の作用の特徴として、自律神経調整や鎮静、鎮痙などで、ストレスに対して有効的です。
真正ラベンダーやゼラニウム、ローマンカモミールなど、フローラルな香りが特徴です。
重合とは、精油のいくつかの分子たちが科学的に結合、つまり合体して大きくなってしまうこと。
重合は、保管時間が長かったり、高温などで起こってきます。
重合が進むと、精油がドロッとした質感になり、蓋を開ける時にベタッとした感じになります。
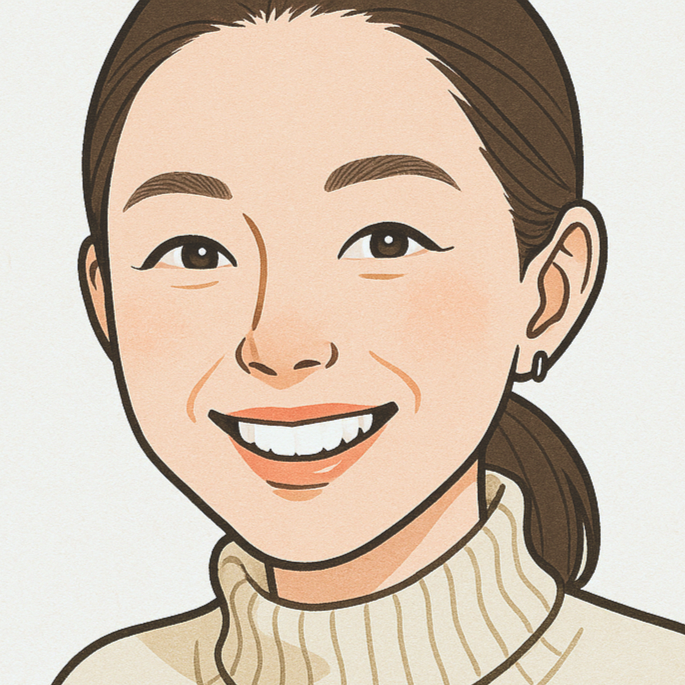
『酸化』『加水分解』『重合』を避ける為にはどうしたらいいか?
空気(酸素)、熱、湿度、時間に注目しましょう。
空気に触れさせない
精油は開封した瞬間から、空気(酸素)との戦いが始まります。
蓋を開けっぱなしは厳禁です。
蓋はしっかり閉めてください。
精油を使っていくと減っていって、精油瓶の中の空気の量が増えるので、つまりは酸化のリスクが高まります。
瓶を振ったり、振動する場所に置いて無いですか?
例えば、いつも持ち歩くカバンの中や、冷蔵庫の扉ポケットなど。
精油が動かない場所での保管がいいです。
熱から逃げろ
保管温度は、10〜15℃が最適とされ、冷暗所保管が良いとされています。
冷蔵庫内で一番温度が高い、野菜室は3〜8℃とされています。
冷蔵庫内は温度が一定しているので、特に暑い夏場、室内が高くなってしまうなら、冷蔵庫(野菜室)の方が良いです。
注意して欲しいのは、2つ。
- 冷蔵庫内の温度と室内の温度の差による結露(水分)。
- 冷蔵庫内の匂い
結露は水分。加水分解の要因になります。
必要な精油だけ取り出して、できるだけ早く冷蔵庫に戻すようにしましょう。
冷蔵庫に、他に食品がある場合は、精油の香りが、その食品に移る場合があります。
精油を密封の箱などに入れたりと、対策しましょう。
室内が涼しければ、室内での保管もありです。
- 直射日光が当たらない(遮光瓶であること)
- 熱は上に行くので、上にあげる場合は、熱がこもってないか確認
- 木箱での保管(木箱の特徴として、調温・調湿機能があります。)
高湿度は避けろ
湿度が高いと言うことは、空気中の水蒸気の割合が高いと言うこと。
風呂場などの水回りは保管場所には向かないです。
調湿・調温機能のある木箱での保管がおすすめ。
時間による劣化からは逃げられない
防腐剤も入っていない天然成分の精油。
古くなるにつれて、香りの深みが増す精油もあります。
例えば、パチュリは年月とともに香りが良くなると有名。開封せずに寝かしておくことも。ただ刺激性は高くなっているので、皮膚塗布は避けてくだい。
精油には使用期限が明記されているので、その期限内で使い切ってください。
精油によって異なりますが、だいたいの目安として、蒸留後3〜5年くらい。
開封すると、使用期限とは関係なく、開封後1年以内。
酸化が早い成分として、αーピネンやdーリモネンがあり、その主成分の精油は、開封後半年以内で使い切るようにしましょう。
例えば、αーピネンは、サイプレスやパインなど針葉樹に多い精油の主成分です。
dーリモネンは、グレープフルーツやレモンなどの、圧搾法で抽出された柑橘類の精油の主成分です。
いずれも、酸化が早く、肌の刺激性が増し、アレルギー性があります。
その他にも、成分のシトラルやシネオールが多く含む精油も酸化が早いです。
例えば、シトラルが多く含む精油は、レモングラスやメリッサなど。
シネオールが多く含む精油は、ローズマリーシネオール、ユーカリラディアータなど。
早めに使い切るよう心がけてください。
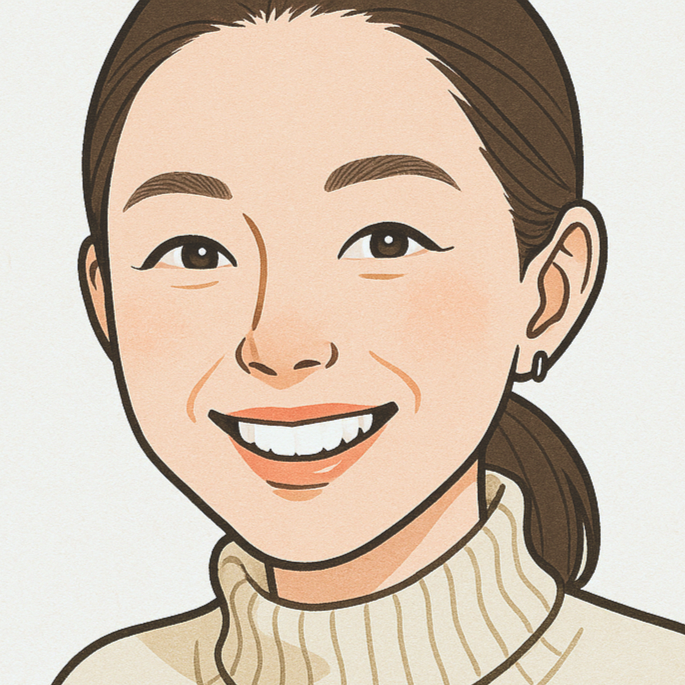
次は安全性を考慮した、保管方法のポイント!
事故が無いように注意しましょう。
⚠️火気厳禁
精油は引火性、可燃性あり、着火源からは遠ざけてください。
精油にはそれぞれ引火点が異なります。
柑橘類の精油、パインやジュニパーベリー、フランキンセンスなど、引火点が30〜50℃と低い精油も多いです。
精油を大量に捨てたり、精油を多く含んだタオル類に乾燥機を使用しないでください。
火災事故につながります。
⚠️プラスチックを溶かす
精油にはプラスチック、ニスや漆などの家具の塗装を溶かす性質があります。
特に柑橘類の精油はその作用が強いです。
キャリアオイルなどで低濃度で希釈されているものなら、その作用は弱まります。
原液の取り扱いには注意が必要です。
精油は基本的にガラス瓶保管です。原液を移したい場合は、ガラス瓶を使用してください。
精油は2重蓋になっていて、中蓋のドロッパーも外蓋もプラスチックの場合がほとんどです。
瓶を寝かせて保管するのはNG。必ず立てて保管してください。
低濃度に希釈したものなら、プラスチックボトルでもいいですが、長期の保管は不向き。
できるだけ早く使い切るようしてください。
⚠️子どもやペットの届かない場所で保管
精油をそのまま飲んでしまったり、皮膚や粘膜、目や耳に入ってしまう危険があります。
誤飲した場合は、口をゆすぐことが出来るなら、口をゆすいで、口の中の残っている精油を出してください。受診先の医師や相談できる機関に相談をして、必要時は受診してください。
皮膚や粘膜、目や耳に入った場合は、すぐに水で洗い流し、この場合も同じく、受診先の医師や相談できる機関に相談して、必要時は受診してください。
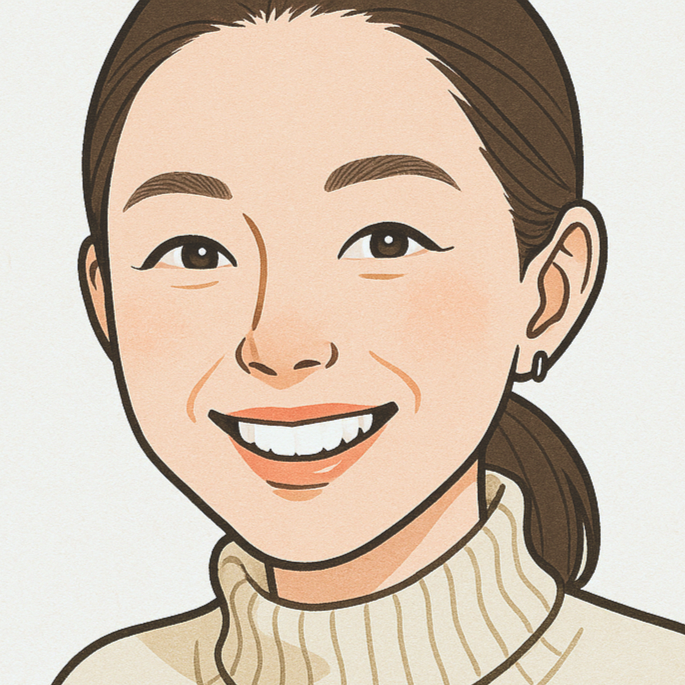
以上が、精油を保管する時に覚えておきたいチェックポイントでした。
安全なアロマライフをお楽しみください。