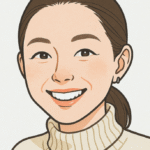子どもとアロマ

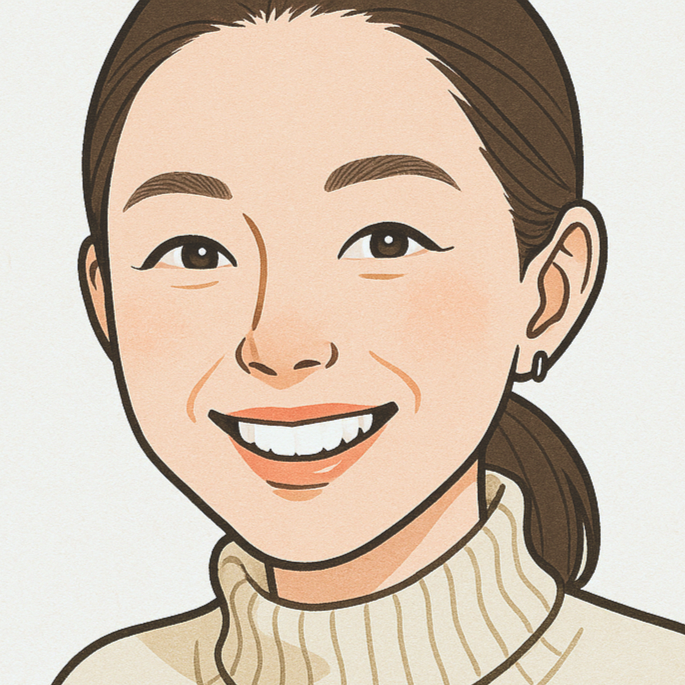
ある特定の香りを嗅ぐと、昔の懐かしい記憶が蘇ることはない?
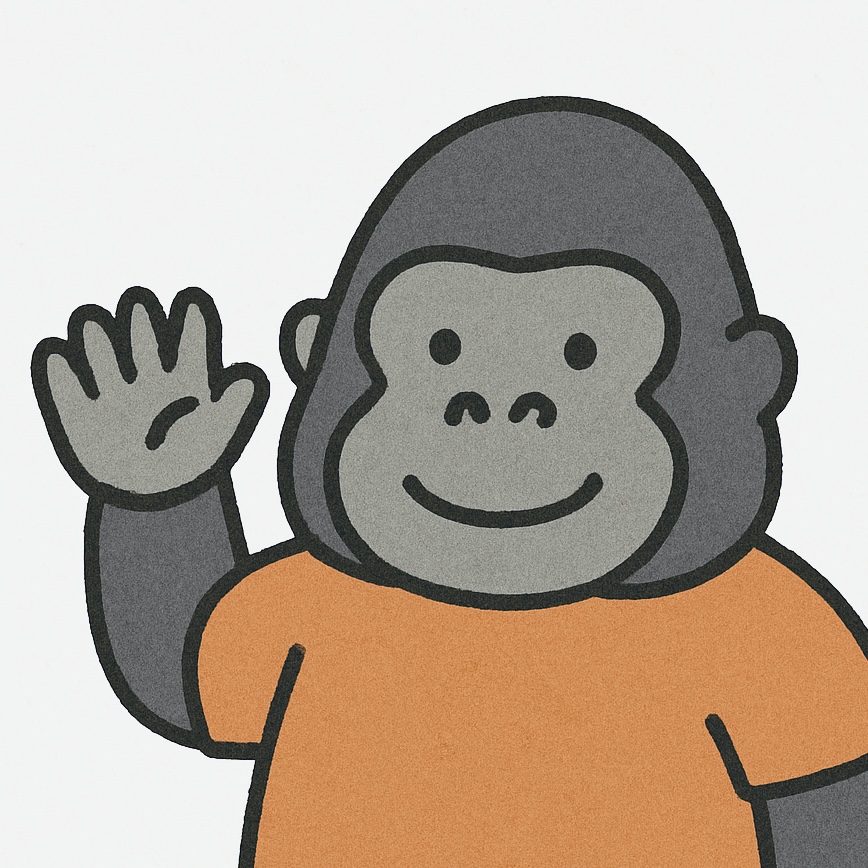
あるある!金木犀の香りを嗅ぐと、小さい頃の住んでた家を思い出すよ。
お母さんが、庭の金木犀をよく飾っていたんだよね。
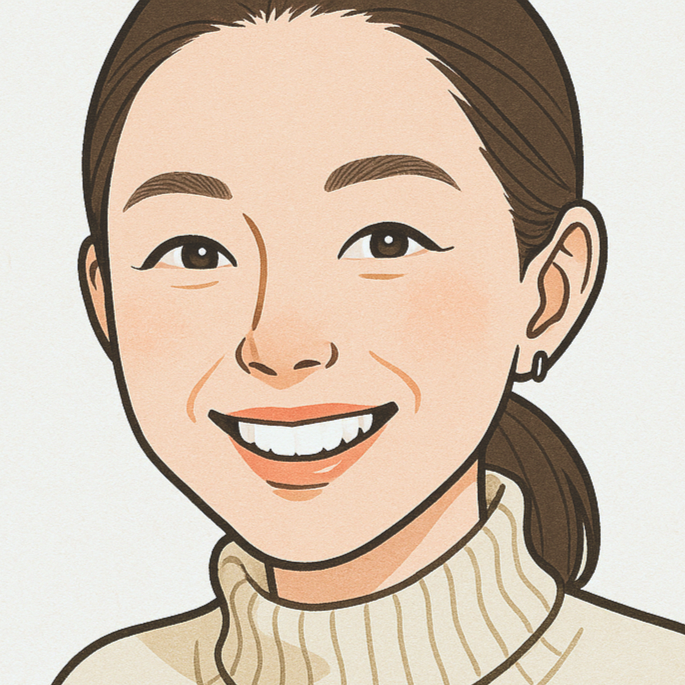
そうなのね。私にとっては、ペンキの匂いは、塗装業をしていた父の後ろ姿が、思い浮かぶ匂いなの。
嗅覚は、最も古い感覚で、大脳辺縁系と言う部分に直接つながっています
大脳辺縁系は基本的生命現象の統制、情動、記憶、潜在意識の発現の場であり、扁桃体や海馬も含みます。
扁桃体は、喜怒哀楽、恐れ、快・不快などの情動反応起こす部位で、大脳辺縁系は感情脳(情動脳)と呼ばれています。
海馬は短期記憶の中枢で、記憶、感情、香りがの3つがしっかり結びついた経験は、より強い記憶として、脳の深層心理まで刻み込まれると言われています。
子どもとアロマをする時、お母さん、お父さん、家族と共にアロマを楽しむことでしょう。
「良い香りだね。」と言いながら、微笑み合うその場はとても幸せの場でしょう。
その香りは、幸せの思い出と共に、子供が成長しても脳の潜在意識に刻み込まれています。
子どもとアロマをする時は、子供にとっても、お母さんお父さんにとっても、楽しむことを心がけて、幸せの思い出を作ってください。
子どもは大人と違います
子どもは、小さな大人ではないです。
なので、用法・用量だけではなく、精油の種類にも注意が必要です。
子供は精油に対する、認容性が低く、香りに対する感覚も大人とは違うので、大人の半量を使えば良いと考えるのは、早計です。
精油を扱う時は、基本的に自己責任が付きまといます。
つまり、子どもの場合、一緒にする大人の責任になります。
子どもは幼いほど、自分の気持ちや症状をうまく言葉で表現できない場合があります。
子供の様子をしっかり観察しましょう。
そうは言っても、劇的な変化は無いので、長期的な観察が必要です。
子どもたちの香りへの感性
子どもは、香りに興味があったり、試したり使ったりするのが好きなことが多いです。
また、大人よりも香りに対するセンスが優れていることも多いです。
子どもは自然と、自分で、自分の救いになるような香りを選ぶことが多いです。
なので、子供自身に精油を選ばせることも、1つの方法です。
芳香の基本
精油の成分が、人体に吸収、作用経路として、①芳香(香りを嗅ぐ)、②皮膚に塗布+芳香(皮膚に塗布する時、おのずと香りが薫ってきます)があります。
つまり、精油の使い方は、ざっくり言えば、「香りを嗅ぐだけ」か、「香りながら皮膚に塗るか」の2通りだけです。
※精油の吸収と作用経路についてはこちらで説明しています。
芳香浴は、生後すぐから可能です。
嗅覚は、個人差はありますが、子どもの方が、大人よりも敏感に感じることができると言われています。
- 毒性や刺激が少ないマイルドな精油から選ぶ。
- 少ない滴数から始める。
- 短時間から始める。
香りが強すぎると、頭痛がしたり、気分が悪くなることもあるので、部屋中にほんのり香りが漂う程度が目安です。
ただ、『嗅覚の順応』と言って、同じ匂いを長時間かぎ続けることで、その匂いを感じにくくなる状態になってしまい、知らず知らず精油の香りが濃くなっているのに、気づかない場合があるので、定期的に換気は必要です。
- 芳香浴の方法は、自然に拡散させる方法、蒸気を利用する方法、ディフューザー等の芳香拡散器を使用する方法など、他にも様々ある。
- それぞれにある一般的な滴数の半分以下から芳香の調整をしてみる。
- 芳香している場所から遠く離れる。
- 定期的に部屋の換気をする。
- 自然に拡散させる方法や、蒸気を利用する方法など、精油が徐々に自然に揮発して無くなる芳香浴は、特に時間は気にする程でも無い。ほんのり香るを意識して、頻回にするのは避けて。
- 芳香拡散器(ディフューザーなど)においては、何時間も芳香し続けるのは避ける。20分を2〜3回/日が目安。
皮膚への塗布の基本
乳幼児の皮膚はまだ完全に成熟していません。
精油は脂質親和性であって、体内に素早く浸透していきます。
皮膚塗擦した数分後に、血中から精油成分が確認されたというデータもあります。
子どもは皮膚の機能性が未熟なので、精油濃度を大人よりも、低濃度に薄くして塗布します。
また、アトピー性皮膚炎や、もともと皮膚が弱い方はさらに低濃度にしたり、皮膚に優しい精油を選びましょう。
- 毒性や刺激が少ないマイルドな精油から選ぶ。
- 精油の濃度を決める。
- 希釈時に使うキャリアオイルを選ぶ。
- 塗布する部位を決める。
| 年齢 | 精油の希釈濃度 | 芳香浴 |
| 0ヶ月〜3ヶ月 | 使用しない | |
| 4ヶ月〜3歳 | 0.1〜0.5% | |
| 4歳〜12歳 | 0.5〜1% |
AEAJでは、3歳未満の乳幼児に対しては、精油を芳香浴以外では使用しない方が良いとしている。
キャリアオイルは、高品質で、酸化していないもの、酸化しにくいものをおすすめします。
セサミオイル、スイートアーモンドオイル、精製されていないホホバオイルなど。
酸化しにくいオイルとしては、ホホバオイルやマカデミアオイルなどがあります。
- 皮膚が薄い顔は避ける。
- 眼や口腔内などの粘膜、デリケートゾーンは塗布しない。
- 皮膚に傷や炎症がある部位は避ける。
刺激が少ないマイルドな精油って何?
まずは、使おうとしている精油の注意書きはしっかりチェックしてみてください。
乳幼児には使用しないなど、記載があるものは、避けましょう。
- 神経毒性が高い、ケトン類含有量が多い精油は使用しない。(カンファー、ローズマリーCTカンファー、スパイクラベンダーなど)
- 皮膚に対する刺激性が高い精油は、避ける、もしくは希釈濃度を下げて使用する。(下記参照)
- アレルギー性(感作作用)のある精油は、避ける、もしくは希釈濃度を下げる、長期連用しない。(下記参照)
- 光毒性のある精油は、低濃度で使用するか、塗布後12時間は紫外線(太陽光線など)に当たらないようにする。(下記参照)
| 刺激強 | フェノール類が主成分とする精油 | シナモンリーフ クローブ タイムCTカーバクロール タイムCTチモールなど |
| 刺激強 | アルデヒド類が主成分とする精油 | レモングラス ユーカリレモン メリッサ(レモンバーム) メイチャンなど |
| 刺激中 | モノテルペン類が主成分とする精油 | リモネン…レモン、グレープフルーツなどの柑橘類の精油 ピネン…ジュニパーなどの針葉樹の葉の精油 |
| 刺激中 | メントールを主成分とする精油 | ペパーミントなど |
| 刺激中 | スパイシー系の精油 | ブラックペッパー ジンジャーなど |
| 刺激低 | マジョラム ゼラニウム イランイランなど |
- 乳幼児、アレルギー体質、疾患や怪我のある皮膚や粘膜への使用は避ける。
- モノテルペン類を多く含んだ精油が、酸化したもの。(特に、ミカン科、マツ科、ヒノキ化の精油)
- イランイラン、レモングラスはアレルギーを起こす可能性があるので、長期連用は避ける。
ミカン科やセリ科などの精油の中には、フロクマリン類を含む精油があります。
フロクマリン類を含む精油を、ある一定量皮膚に塗布し、日光に当たると皮膚炎を発症する可能性があります。
光毒性がある主な精油には、圧搾法で抽出されたベルガモット、ビターオレンジ、グレープフルーツ、レモン等のミカン科が挙げられます。
使用する場合は、低濃度で使用するか、塗布後12時間は紫外線(太陽光線など)に当たらないようにしましょう。(24〜72時間は日光に当たらないと謳っている文献もあり。)
同じミカン科でも、スイートオレンジ、マンダリンには光毒性は無いので、安心して使用できます。
まずは、安全性の高い、真正ラベンダーやカモミール、マンダリン等から始めてみるのをオススメします。
それでも、心配な場合は、フローラルウォーター(芳香蒸留水、ハイドロゾル)から始めてみても良いでしょう。
パッチテストをやってみるのも一つの策
より安全性を確認するのに、パッチテストは有効です。
ただ、パッチテストを正確に行うには、48時間〜1週間かかる為、低年齢である程、子どもに行うのは困難な場合が多いでしょう。
下記の方法は、一つの方法案として、参考にしてください。
精油が入っていない、使用する予定のキャリアオイルのみ
使用する予定の精油が、使おうと思っている濃度(0.1〜1.0%)でキャリアオイルに希釈されたもの
低年齢の場合は背中の方がいいでしょう。目に付くところや、手が届きやすいところは避けた方が無難でしょう。
塗布した部位が見失う場合は、フィルムテープ上に油性マジックで丸く囲みます。
赤くなっていないか、痒くないか、何らかの変化の有無を確認します。
炎症反応が現れた時点で、テストは中断し、水で洗い流してください。
何らかの炎症反応があれば、その精油は使用しないようにしましょう。
パッチテストは時間がかかるので、どこまで評価するかは、ご自身の判断になってしまいます。
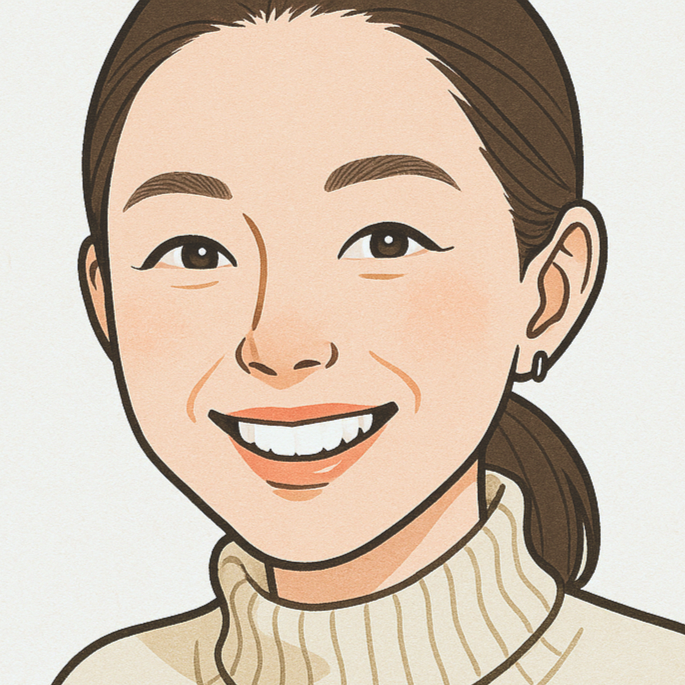
赤ちゃんに、始めて離乳食を食べさせた時の、あの頃を思い出すわ〜
1種類ずつ、大丈夫か、様子を見ながら食べさせたよね。
お母さん、お父さんの心の安らぎが、子供の安心につながる
親の感情の揺れ動きは、子供の感情表現や行動、そして精神的な安定に影響与える可能性があります。
親がバタフライハグを実践することで、子供の心の状態を落ち着かせ、やすらぎを与える効果が期待できます。
バタフライハグは、過度に興奮した自分をリラックスさせ、落ち着かせるのに役立つ、セラピー的介入の方法で、効果的なグラウンディングの技術です。
バタフライハグの方法
今の気分は?体の調子はどうかな?自分自身にフォーカスします。
胸に手がタッチした瞬間、脳はその手に集中します。
他の考えは無くなり、その手だけに頭が一杯になります。
これがタッチングの効果です。
呼吸はゆっくり、数分繰り返します。
バタフライハグの前に、手のひらに、自分が好きな精油や、直感的に選んだ精油を、手のひらに1滴、垂らしましょう。
手の温度で、精油を温め、手をヒラヒラさせたり、鼻に近づけて、ゆっくり呼吸しましょう。
そして、バタフライハグを始めてください。
(精油はマイルドな精油を選んでください。)
おすすめの精油をいくつか紹介しています。
精油は単品で使用しても良いですし、数種類ブレンドしても良いです。
年齢が幼いほど、最初は単品で、徐々にブレンドして導入してみましょう。
子どもに選択させてみましょう。
お母さん、お父さんが好きな精油を紹介してみてもいいですね。
どんなに薬効が良くても、子どもが拒否するのは使わないで。
アロマディフューザーで芳香
芳香浴の方法は色々ありますが、一番のおすすめはディフューザー。
なぜなら、他の芳香方法に比べて、部屋全体に香りが行き届きやすいから。
ディフューザーには超音波式とネブライザー式があります。
超音波式は、水に精油を加えて、ミスト化して拡散させるので、加湿にもなりますね。
ただ、水垢やカルキが付きやすく、機器のお手入れを定期的にしないといけないです。
ネブライザー式は精油を圧縮空気によって微粒子状にして香りを拡散させます。
水に混ぜたりしないので、香りが安定してます。
ただトロミの強い精油は目詰まりしやすいので注意。
お手入れは超音波式よりは頻度も少なく、お手軽感はあります。
どちらの機器も、だいたいタイマー機能が付いているのが嬉しいですね。
置く場所は気をつけて下さい。子どもやペットが届かない場所に置いて、事故がないように注意して下さい。
就寝30分〜1時間前から、寝室のディフューザーを付けておきます。安全のため、就寝前に電源を切っておくのもいいですし、タイマーを付けておくのもいいです。
- マンダリン
- ベチバー
- オレンジ
- ネロリ
- ローマンカモミール
- ローズ
1日の始まりの時、勉強を始めようとする時、心を落ち着かせ、より注意深く、集中するために。
- ラヴィンサラ
- サンダルウッド
- グレープフルーツ
- ラベンダー
- ベルガモット
- レモン
- スイートバジル
アロママッサージでタッチセラピー
子供はいくつになっても、多くの愛情を必要とします。
どの年代の子供も、撫でられたり、マッサージをされるのは好みます。
心配事がある時に、子供たちを慰めるには、愛情を込めて、アロママッサージをしてあげるのが1番と思います。
思春期においては、自分の感情を表に出せなかったり、体の接触を拒否してしまうと子どもは少なくありません。
無理にする必要はありませんが、精油を選ばせて、手や足ならアロママッサージを受け入れてくれるかも。
マッサージしていくと、頑なさが解けていき、リラックスして話ができるようになります。
- 精油は目的によって選んでも良いですが、コミュニケーションの一手段として、一緒に香りを試しながら選んでみましょう。
- マッサージ部位も子どもと話しながら決めましょう。戸惑っているようならば、まずは足。受け入れが良ければ、次のマッサージの機会では、手を。次に肩、背中へとアプローチしていきましょう。
- マッサージは難しく考えず、呼吸に合わせて、ゆっくりゆっくり、リズム良くマッサージしていきます。
- マッサージの時間は決まりはありません。1分でも、10分でも、子どもとお母さんやお父さんの心が繋がることが目的なのです。
子どもにメッセージを送ってみましょう。
マッサージの途中に、足の裏、手の平、背中に、「すき」「あいしてる」「ありがとう」と指でなぞって下さい。
声は出さなくて、大丈夫。
ただ、子どもに、あなたの心を伝えて下さい。
- 毒性や刺激が少ないマイルドな精油から選ぶ。
- 精油の濃度を決める。
- 希釈時に使うキャリアオイルを選ぶ。
- 塗布する部位を決める。(オイルの必要量を決める。)
①〜④まで決めたら、早速作ってみましょう。
例えば:0.5%濃度、オレンジのアロマオイルを20ml作りましょう。
容器(ガラスや陶器のお皿でも、ボトルでも使いやすい物)に、分量20mlのキャリアオイルを入れて、オレンジの精油を2滴入れて、混ぜます。出来あがり!
20mlの0.05%→ 20ml×0.005=0.1ml
0.1mlの精油が必要。精油は1滴、0.05mlであるから、
0.1ml÷0.05(精油1滴)=2滴
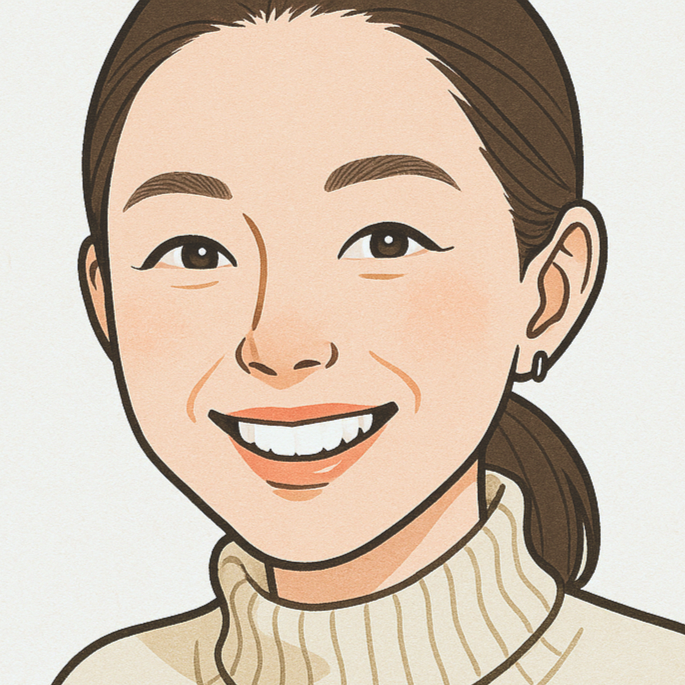
作ったアロマオイルは、使う度に、必要量を作る方がいいですね。
お気に入りのブレンドアロマオイルがあるなら、作り置きしても良いですが、時間が経てば、どうしても香りは飛んでしまいます。
保管する時は、蓋付き容器で、直射日光が当たらない、涼しい場所で保管して、清潔に扱って下さい。
できるだけ、早く使い切ってね。
香りを持ち運ぶ、アロマスプレーとロールオン
子どもが落ち着く、お気に入りの香りがあるのなら、外出先にも持って行きたいですよね。
例えば、お泊まり先で、いつもの香りがあれば眠れるとか、緊張する場で、その緊張をほぐしてくれるような香りがあれば、心強いはずです。
アロマスプレーは、空間や布製品とかにスプレーできます。
ただ水分が多い分、劣化が早いので、早めに使い切ること。
冷蔵保存すれば、まだ長く保存できます。
ロールオンはアロマオイルです。
手首や首筋など、皮膚に塗布します。
自分だけが香るので、周りを気にしなくても良いですね。
劣化しにくいオイルで作るのがいいでしょう。例えば、ホホバオイルなど。
例えば:外泊時、いつも通り眠れるように、枕元にかけるスプレーを作りましょう。
1%濃度、総量30mlで作ります。
- スプレーボトルに3mlの無水エタノールいれます。
- 精油は6滴入れて、軽く振って混ぜます。(例えば:マンダリン4滴、ベチバー1滴、ローマンカモミール1滴)
- 水道水(精製水でも)を27ml入れて、総量30mlにします。
- スプレー直前に、必ずよく振って使用します。
目に入らないように注意して下さい。
ロールオンの容器に合わせて総量を決めて、精油の滴下数を決めましょう。
例えば:1%濃度の場合
5ml:精油1滴
10ml:精油2滴
先に容器にキャリアオイルを入れて、精油を入れて、蓋をして振って混ぜます。
アロマパッチ
アロマパッチに精油を垂らして、子どもの服の襟元や背中に貼ることで、ほのかに香るというグッズ。
精油が直接、皮膚に付かないように注意して下さい。
最近は様々なアロマグッズがあります。
ご家庭に合わせて、試してみるのも楽しいものです。
アロマバス
湯を張った浴槽に、精油を入れることで、蒸気と共に芳香成分が広がり、吸入することが出来ます。
精油は水に溶けないので、必ずバスベース(乳化剤)と精油を混ぜて、お湯に入れて下さい。
代用としては、無水エタノールや天然塩、重曹、クエン酸、ハチミツなど。
工作が好きな子なら、一緒にバスボム作りも良いですね。
作っている時も、芳香している状態ですし、一緒に作業をする楽しさは、良い思い出として、刻まれていきます。
初心者に受け入れやすいミカン科の精油
まず、子どもに好まれやすい精油として、ミカン科が挙げられます。
- マンダリン (Citrus reticulata/Citrus nobili)
- スイートオレンジ (Citrus sinensis)
- ベルガモット (Citrus bergamia)
- レモン (Citrus limon)
ミカン科の圧搾法で抽出された精油には、フロクマリンという成分が含まれている精油が多いです。
フロクマリン類を含む精油を、ある一定量皮膚に塗布し、日光に当たると皮膚炎を発症する可能性があります。
これを光毒性と言います。
使用する場合は、低濃度で使用するか、塗布後12時間は紫外線(太陽光線など)に当たらないようにしましょう。(24〜72時間は日光に当たらないと謳っている文献もあり。)
ただ、同じミカン科でも、フロクマリンの含有量は異なり、スイートオレンジ、マンダリンには極微量の含有量であるため、光毒性を気にせず、安心して使用できます。
またブランドによって、フロクマリンが検出されない精油もあるので、成分表を確認すると良いでしょう。
注意が必要な、フロクマリンですが、「暗闇の一筋の光」と言うように、太陽の光が満ち溢れた元気いっぱいな夏の日を連想させるような香りで、憂鬱な気分を和らげ、爽快、リフレッシュさせてくれる作用があります。
- プチグレン (Citrus aurantium var.amara fol.)
- ネロリ (Citrus aurantium var.amara flos.)
プチグレン、ネロリはどちらもビターオレンジから抽出しており、プチグレンは葉から、ネロリは花から、どちらも水蒸気蒸留法で抽出されています。
どちらも、精神に対する作用が優れており、鎮静、リラックス、抗うつ作用があり、沈んだ気持ちを引き上げてくれます。
一般的に、ネロリは価格的に高価な精油であり、プチグレンは手に入れやすい価格となっています。
プチグレンは「貧乏人のネロリ」と言われ、微量成分が多く、作用もある程度ネロリと似ています。また真正ラベンダーとも主成分が似ていることも特徴の一つです。
心をスッキリ落ち着かせてくれる瞑想的な精油
鎮静、抗うつ、リラックス作用のある精油で、精神を落ち着かせ、不安や落ち込んだ気持ちを解消、平常心を取り戻してくれます。
- ベチバー(Chrysopogon zizanioides)
- フランキンセンス(Boswellia carterii)
- サンダルウッド(Santalum album)
- パチュリ(Pogostemon cablin)
ベチバーは根から抽出されており、土のような香りで、「足を地につかせる」グランディングの効果あり、心は落ち着かせながらも、頭はすっきりするので、創作活動の時などに良いです。
フランキンセンスは、呼吸を深めゆっくりする作用があり、場の浄化に使われたりします。
サンダルウッドは、白檀のことで、お香や扇子などの材料で日本人に馴染みがある香りです。心地よく甘く癒される木の香りで、心の平穏をもたらしてくれます。
パチュリの香りは、人によって好みが分かれなすが、ブレンドすることによって、香りに深みが増します。精油には珍しく食欲を抑える作用もあると言われており、ダイエットをしたい人にもオススメできます。
バランスを整える精油
- ローマンカモミール(Chamaemelum nobile)
- ローズオットー(Rosa damascena)
- ゼラニウム(Pelargonium x asperum)
- 真正ラベンダー(Lavandula angustifolia)
- クラリセージ(Salvia sclarea)
- ラヴィンサラ(Cinnamomum camphora CT.cineole)
ローマンカモミールは、強い鎮静作用が特徴です。子ども特有の情緒からくる腹痛にも、希釈したオイルで、腹部をゆっくりマッサージするのは有効です。また肌が弱い方にもオススメで、高価な精油でありますが、わずかな量でも充分な効果が得られます。
ローズオットーは、強い調和、バランス作用が特徴です。「愛の香り」と呼ばれており、硬くなった心を開かせてくれます。皮膚にも優しく、高価な精油でありますが、わずかな量でも充分な効果が得られます。
ゼラニウムは、心と体のバランスを整えてくれます。ホルモン調節作用もあり、思春期に起こりうる生理不順にも良く、香りが強いのが多少気になりますが、他の精油とブレンドすると良いでしょう。
真正ラベンダーは、昔から万能薬として親しまれていました。様々な作用がありますが、心と体のバランスを整え、セロトニンの分泌を促してくれます。他の精油とのブレンドの際、刺激を緩和してくれるクエンチング作用もあります。皮膚への刺激も少なく、安全に使用できます。ただ、血圧を下げる作用もあるので、低血圧の方は注意が必要。
クラリセージは、リラックス、鎮静作用あり、インスピレーションを与え、創造性を高めてくれます。通経作用があるので、月経時の出血が多い日は、出血過多の可能性あり、クラリセージでのアロママッサージは避けた方が無難です。
ラヴィンサラは、疲労感を緩和させ、気持ちも引き上げ、頭もすっきりしてくれます。その一方で不眠にも良いとされています。また強い抗ウイルス作用あり呼吸器系の感染や室内の空気の殺菌にも効果があると言われています。
眠気が覚まし、活力アップする精油
- ローズマリー・シネオール(Salvia rosmarinus CT.cineole)
ローズマリーシネオールは、活力向上作用があり、低血圧の人や、朝起きるのが辛い人に、1日の始まりにオススメの精油です。高血圧の人は避けるのが無難です。眠前に使用する場合は、鎮静作用のある精油とブレンドしましょう。
元気が出て、気持ちがリフレッシュする精油として、最初に紹介した柑橘系の精油もおすすめです。
- 100%天然由来の精油を選んでください。
- 遮光瓶に入った精油を選んでください。
- 直射日光が当たる場所は避けて、涼しい場所で保管し、しっかり蓋を閉めてください。
- 精油は引火性、可燃性があるので、火気厳禁です。
- 子どもやペットが届かない場所で保管してください。
- 使用期限を守って、劣化した精油は使用しないでください。
- 精油は飲まないでください。
- 眼に入らないようにしてください。
- 精油を直接肌に塗布しないでください。
- 妊婦中は避けないといけない精油があります。使用前に調べる必要があります。
ここで少し、私の話を。
私には小学生の息子がいます。息子は典型的な自閉症で、今は支援学級に通っています。
そんな息子がまだ小学生になる前の頃の話しです。
息子は身体は丈夫な方でしたが、たまに風邪や発熱はありました。
病院に連れて行くのも大変、処方された薬なんて飲ませられたことなんてありません。
唯一使えた薬は、坐薬と軟膏類と貼付剤。
坐薬を使うときは発熱で元気がないので、抵抗されますが、隙をついて坐薬を入れます。
貼付剤は背中にこっそり貼ります。
軟膏類は風呂上がりだったら、なんとか塗れました。
触れられるの嫌い、着替えは風呂のタイミングでしか出来ず、パジャマなんか着せたこと無いです。翌日の服を着せて寝かせていました。
食事は気をつけていましたが、偏食もきつかったですね。
散歩に行くと何時間も家に帰られない、一瞬も目を離せない。時々来る癇癪に、イライラ。身体的にも精神的にも疲れていました。
そんな時に出会ったのが、アロマ。
フラフラ買い物に行った時、突発的に精油1本とアロマデュフューザーを買ってきて、部屋中香らせていました。
どんなにイライラしていても、「あ、イライラしてるな。アロマしよかな〜」と思って、精油を出して準備してデュフューザーのスイッチを入れるという動作は、ちょっとだけ心に余裕を作ってくれました。そして、深呼吸で香りを感じると、不思議と前向きな気持ちになりました。
そこからアロマセラピーについてもっと学びたくなって、スクールに通い始めました。
体と心に統合的に、香りとタッチでアプローチするアロマセラピーは、できない事が多い息子には本当にピッタリでした。
劇的な変化はありませんが、毎日の関わりの中で、穏やかに成長促すような優しさが、私は大好きでした。
コミュニケーションが取りづらいので、息子の本心は分かりませんが、触れられるのが嫌いな息子が「マッサージ〜」と言って、床にゴロンとなる姿を見ると、私は嬉しくて息子に飛びついちゃいます。
もちろん今でも、息子の気持ちがわからず、お互いイライラしたり、暴走する息子を見失わないようにヘトヘトになるまで追いかけたり、ハプニングは沢山あります。
それでも、いつでもアロマが、私と息子を優しく繋げてくれます。
以上、私と息子とアロマのお話でした。